伊吹翼と拗らせクラスメイト男子
この投稿は 東京工業大学アイドルマスター研究会 Advent Calendar 2020 ( AdC2020 ) 22日目となります。
前書き
こんにちは。東京工業大学アイドルマスター研究会のカラスムギです。
この記事ではミリオンライブの伊吹翼をテーマにしたSSを掲載しています。ここでのSSの意味は、二次創作小説のこととします。
翼をオタク目線で書いたSSはいつか書きたいと思っていたので、今回の機会に筆をとることにしました。
よろしければ本編にご付き合いください。
※翼のセリフ少なめです。

本編
ブーーーッ。
信二は、会場に鳴り響くブザーに驚いて体をこわばらせる。
それは開場の合図だったようで、続けて深紅の幕がゆっくりとあがっていった。右隣に控える友人の慧介は慣れた様子で、ヒューっと声を上げている。コンサートライトが揺れる客席からは、続けて同じような奇声が二、三あがった。
(場違いなところへ来てしまった)
後悔しても遅い。信二は覚悟を決めると、ステージに駆けてくる少女たちへ目を移した。
***
とある都内の学び舎。校庭の樹は緑から茶へと衣替えをする途中だ。冷たくなった風がさわさわと葉を鳴らしている。
窓際の信二は、その寒々とした演奏をながめていた。朝礼にはまだ早く、埋まった席は多くない。校門からアリのように列をなす顔は、判別がつかなかった。信二の後ろでは数人の女子が井戸端会議を開いている。こんな時間でも元気なもので、甲高い声が響く。
「——でさぁ、昨日発売のりるきゃんの特集なんだけど——」
「——わかる~。あれホントかわいいからさっそく——」
断片的に聞こえてくる会話は、どうやら少女漫画雑誌の特集についてらしい。
(こどもだな)
彼は気に入らないという風に鼻を鳴らした。人目をはばからず大きい顔をしていても、同い年とは思えないくらい幼く思える。メイクがどうのこうの話しているが、お遊びみたいなものだろう。
「てかツバッティー、今日は来るの早いじゃん」
「今日はついでだって言って、パパが送ってくれたんだ~。お仕事前にっ」
「ツバッティー愛されてんじゃ~ん。コノコノ」
「こんな可愛い娘ならいくらでも送りたいっしょ」
ツバッティーと呼ばれた少女は、脇の友人から脇をつつかれているようだ。伊吹翼という名のクラスメイトである。彼女たちの会話は、伸ばされた語尾が耳にねっとりと絡みつく。その内容は意識しなくても頭の中に残り、こびりついてしまう。
(甘やかされてるんだろうな)
信二は納得した。いつも遅刻スレスレなのも、強く注意する親がいないのだろう。教師の中にも、翼を猫可愛いがりしているものがいる。それだけ愛される才能があるということなのかもしれない。媚びた言葉づかいのせいか、それとも風貌が優れているせいかは知らないが。
そう、翼の容姿は飛びぬけていた。黒いセーラー服の上からでもわかる整ったプロポーションもそうだ。押しあげられた胸のリボンをチラチラ見ている男子も多い。だが、特筆すべきなのは顔立ちだろう。美しいものは数学的に美しいとも言うが、その最たる例と言ってよいかもしれない。海外モデルのようなそれはしかし、ふっくらとした幼さを残している。血色のよい頬をくしゃっとさせた笑顔は、天使のように天真爛漫に見える。翼はそんな矛盾した魅力をあわせ持っていた。
人生こういう人間が得をするのかもしれない。信二はそう思うと、やるせなくなって親指の爪を噛んだ。
「慧介」
こちらの席へ近づく友人に、信二は手をあげて応えた。給食が終わった小休止の日課だ。他愛のない世間話に花を咲かせようと、彼は近くの空き椅子を引きずってきた。
慧介は、信二がよく話すクラスの友人だった。この黒縁メガネの男子は外見はぱっとしない上にアイドルオタクだが、信二にとっては特別なクラスメイトだった。信二の話を笑顔で聞いてくれるのは、彼くらいだったからだ。
「信二、頼みがあるんだが……」
話題がひと段落したところで、慧介は切り出した。少し言いにくそうにチラチラと顔をうかがってくる。怪訝そうに信二が先をうながすと、彼は再び口を開いた。
「今週末に765プロのライブがあるんだけど、連番者が急に行けなくなったって言うんだ……信二、一緒に行ってくれないか」
「ライブ? 何で俺がそんなもんに行かなきゃならないんだよ」
「頼むって。もう直前で、引き取り先が見つからないんだよ。信二しか頼める相手がいないんだ」
値引きするからさ。そう言って両手を合わせる友人を前に、信二の表情は硬い。
(やっかいなことになったな)
どうやって断ろうか考えるが、本当に困っている風の友人に強くは言いにくい。信二は言葉を選んで目を泳がせる。
「あっ、そういえば……!」
声をあげると慧介は後ろをキョロキョロと確認する。何をやっているのかと信二が半目になっていると、ずいと顔を近づけて内緒話の体勢をとる。ご丁寧に左手を口元に添えるおまけ付きだ。
「お前、伊吹さんのこと好きだろ」
「はぁ?!」
声が大きいぞ、と眉をひそめる友人の頬を人差し指でつつく。
「全然、全く、これっぽっちも、好きじゃねぇよ」
周りの学生がチラチラ目を向けているが、関係ない。
信二は唇をとがらせて抗議する。だがニヤニヤ笑いを浮かべる慧介には、のれんに腕おしのようだ。
「照れちゃって。その伊吹さんだがな、この公演に出てくるんだぜ。アイドルとして」
(!)
アイドル。例の女子グループからそんな話題が聞こえたことがあった……気がする。その時は聞き流したが、別口から再び伝えられると実感が出る。
目を見開く信二。慧介は学ランのポケットから長めの紙片を手に取り、机にトンと差し出す。
「チケット。置いとくぞ」
「ちょっ」
席を立とうとする慧介の左腕をつかんで制止するも、言葉が出ない。畳みかけるのはずるい。学校にチケットなんて持ってくるな——ではなく。
「好きじゃねえって言ってるだろ」
こういう誤解は早めに解いてしまわなければ、禍根を残す。我々中学生にとって、こういう噂は致命的なのだ。
だが、にらみつけても相手の瞳にさざなみが立った様子はない。
「いつもあんなに意識してるのにか? 俺はてっきり——」
何を言っているんだこいつは。だが、周りにはそんな風に映っているのだろうか。俺が伊吹に向けているのはあきれた視線だけなのに。
信二は慧介からの不当な評価に反論しようと息巻く。
だが、時間切れのようだ。慧介の椅子の主が帰ってきてしまった。慧介は腰の下のものを返却すると、考えのまとまらない信二を置いて戻っていってしまった。
気づいた時には机上の紙きれが1枚、信二を見つめていた。週末のライブの入場券だ。
(やられた……)
次の休み時間にでも返そうと思い、教科書の間にはさむ。ちらっと慧介の席に視線を投げると、不快な笑みとぶつかった。
絶対突き返してやろうと決めて、信二はどう言ってやろうかと頭を抱えた。慧介は俺が熱い視線を伊吹に向けていると思っている。視線の意味を誤解しているのだ。
あんまり心を砕いていたものだから、チョークのコツコツという音が鳴って初めて、信二は理科の授業の開始を知った。引き戸の音にすら気付かなかった。
ぼそぼそと解説するおじさん教師には目もくれず、信二は腕組みをして集中したふりをしている。実際のところ彼の脳内を占領しているのは、次の慧介との会話のシミュレーションだけだった。
——嘘である。右方の明るすぎる茶髪と、寝ぐせのようにハネた髪型が雑念を呼び起こす。信二はそれができるだけ目に入らないように考えをまとめるしかなかった。
伝えるべきことはどんどん増えてきて、とても授業の合間の小休止で話は終わらない。だから信二は、勝負を放課後と決めた。あいつのとんでもない思い違いを正してやらなければ。
***
キーンコーンカーンコーン……。
高い秋空の下、鐘の音が響いた。決戦の合図としては申し分ない。
信二は真っ直ぐ慧介の顔面へ向かった。
「慧介、まずこれは返す」
折れ目はつけていないはずだ。信二はあえて周りにも聞こえるように声を張る。
「それと、お前の勘違いを正してやらないといけないな」
「勘違いね」
「俺は伊吹のことなんて何とも思ってない。いつも目障りに思ってるくらいだ」
さっきも考えの邪魔だった。
慧介は簡単な相槌を返す。流れは自分にあると信二は思った。
「遅刻はするわそれを悪びれもしないわ。遊ぶことばっか考えてる。しかも声がでかいから意識しなくても気になるんだよ」
気にはなるが、その意味が違うのだと信二は主張する。
それを聞いても慧介は黙ったままだ。だから信二は、自分が優勢だと判断した。
「掃除もサボるし廊下は走るし視界の端をチラチラするし、周りの迷惑を考えてほしいよ」
「なあ」
「なんだよ」
不満をたれ流す信二に、慧介は複雑そうな顔で口をはさんだ。
「信二、いつも伊吹さんのこと見てるだろ。確かに気に入らないところもあるんだろうけど、そうじゃない表情もしてたぞ。——お前、いつも切なそうじゃないか」
「っ、それは……ただの劣等感だよ」
言う予定になかったことを言わせるな。
信二は、親にも先生にも『真面目』としか褒められたことのない、そういう人間なのだった。伊吹には無遠慮さが周りを傷つけていることを自覚してほしい。彼はそう思った。
裏切られたような気分になって、信二は話を切り上げてしまいたくなる。チケットはもう返してやったのだ。これ以上の用はない。
「待てよ信二、伊吹さんはお前が言うように他人の気持ちを考えない人じゃない。そこは訂正させてくれ」
腰をあげようとする信二の手をつかむ慧介の瞳は、信二の不意をつく鋭さだった。
小学生の安田慧介は、目が悪かった。眼鏡はかけていたものの、年々視力が落ちていった。短期間に何度も買ってもらうのが忍びなくて、後ろの席でも目を細めて我慢していたのだった。板書がとれないものだから、彼の成績は低迷した。
初めにそれに気づいたのは、親でも先生でもなく、クラスメイトの女の子だった。席替えで近くになった彼女は、後ろだと好き勝手出来ていいね~なんて大声に出して、先生にあきれられていた。能天気だな、なんて慧介も笑った。しかし黒板から遠くなってしまって、彼の心は泣いていた。
そんな彼の顔を見て、彼女は心配して声をかけた。「大丈夫?」そんな月並みな言葉だ。慧介は「ちょっと目が悪いだけ。全然平気」なんて強がって見せた。でも彼女はすぐに天井に届くほど高く手をあげて「先生! 慧介くんが黒板見えないって!」なんて言った。「前の人、誰かかわってあげてよ!」なんて。彼女の近くの席は大人気で、じゃんけん大会がひらかれた。先生も笑っている。楽しい催しだ。
伊吹翼は、その頃から太陽みたいに輝いていた。穢れを知らない白色光だと、慧介は子供ながらに思った。
慧介の話を聞いても、信二は納得していないようだった。眉間にしわを寄せている。
言いたいことは多かったが、一番気になったところを指摘した。
「その話、お前は助かったかもしれない。だけど、顔に出さないだけで延長にうんざりしていたやつもいたんじゃないのか」
立場が偏りすぎている。慧介がこんなに伊吹贔屓だったなんて知らなかった。
「そうかもしれない。でも、伊吹さんは正しいと思ったことを素直にできる人だと思う」
深く考えないところはあるかもしれないけど……。慧介はそう遠慮がちに付け加える。
信二だって、翼の性格が悪いなんて思ってない。だが、信二の方こそ一方的な立場に立っていたのかもしれない。
「だからこそ、ライブでの伊吹さんを見てみなよ。印象が変わるかもしれないだろ」
一理ある。慧介は自分の目で見て確かめろというのだ。正論なのは理解できた。
迷った末、信二は友人の机から券を拾い上げた。
「行ってやってもいいぜ。ただし、媚びるだけのつまんないものだったら承知しないからな」
「ああ、その時はチケット代はこっち持ちでいいよ」
「じゃあ俺が伊吹に惚れたら2人分出してやる」
2人の男子生徒は笑い合う。決闘は、和解と相成ったのであった。
***
曇り空の下、信二はため息をついた。コートが必要な陽気ではないが、海風に吹かれると体感温度は一気に下がる。待ち合わせの広場にはいかにもな風体の男性が沢山いて、肩身がせまかった。だから友人の顔を見たとき、信二の頬は思わずゆるんだのだった。手をあげて挨拶をする相手に、彼は声を返した。
慧介はやけに高揚していて、今日出るらしいアイドルの話を延々としてきた。彼が好きなのは24歳のアイドルで、歌唱力が高いらしい。低身長で可愛い外見とお姉さんぶっているギャップがいいと言っているが、正直ピンとこない。
「あずささんと同じ公演に出てたのを見てはまっちゃったんだよ」
てっきり伊吹のファンとばかり思っていたが、違うようだった。人間としての好きとアイドルとしての好きは別物だとか言っている。ついでに推しと彼女にしたいと結婚したいも違うらしい。……さっぱりわからん。
それからは慧介の支持するまま会場に入り、開演時間の今に至る。暗い中でも友人の貧乏ゆすりが伝わってきていた。
観客が待ってましたと声を上げる中、ステージにはアイドルたちが入場し、最初の曲を披露する。ライブシアターでの公演を喜ぶ、キラキラした歌だ。
紺のスカートに紅白のトップスがよく映える。厚手の生地はライトを反射し、ステージから遠い彼らにもそれが特別なものであることがわかった。
だがアイドルへの認識が大きく変わるとは、信二には到底思えなかった。ダンスの完成度はまちまち。歌は所々音程が揃っていなくて、不協和音を奏でた。信二たちより年下のアイドルも数人いるようだから、こんなものなのかもしれない。それよりも、周囲の野太い掛け声が気になってしまう。
(こんな状況で心地よく歌えるのか?)
2段のフォーメーションの1段目、左端近くに彼女はいた。強い光を受けて金色に見える髪の毛が、衣装のスカーレットとのコントラストで際立つ。ダンスは周りより見栄えがよい。優れた運動神経のおかげだろうと信二は納得した。10人以上がいっぺんに歌うので、歌唱力の方はよくわからない。伊吹の表情を見ると、クラスでのものと変わらないようだ。よく言うと「どこでも自然体」悪く言うと「何も考えてない」だろうか。
そうこうしているうちに、1曲目が終わった。そのまま1人ずつ、右から自己紹介を始めていく。1人の挨拶が終わるごとに、観客が騒いではやし立てた。名前を叫ぶものもいる。
アイドルごとに、反応の大きさが違うような気がする。信二にはそれが人気の指標のような気がして、その差を聞くのがつらかった。もちろん、ランキングと完璧に一致するものではないだろうが、彼女たちはどんな気分でこれを耳にしているのだろう。グッズの売り上げなどでも、差を痛感したりするのだろうか。
信二は、幸せそうなアイドルたちの苦労の一端に触れた気がした。メンタルが強くないとやっていけないのだろうか。
翼の番が来た。学校と同じか、いつもより少し高いテンションだ。
「みんな、きてくれてありがとー! 今日は、とくに練習をがんばった曲があるので、楽しみにしててねー! 私のこと、ちゃーんとみててくださいね!」
伊吹が素なのは間違いなさそうだ。平均より少し大きいくらいの歓声が沸き、拍手が鳴る。人気はある方なのかもしれない。性格にむらはあっても、ビジュアルは一級品なのだ。何でもこなす伊吹の器用さがまた証明されたようだ。信二の握りこんだ手のひらに、爪が少し食いこんだ。
最後の1人がマイクをおろすと、彼女たちははけていった。ステージはつかの間の暗闇と無音に包まれる。
イントロが流れると同時に照明が舞台を染めた。次の演目だ。ユニットらしい、アイドル4人組が歌っている。ピコピコした電子音が特徴的な、こどもっぽい曲。児童向けの教育番組を彷彿とさせる。大きな歓声があがるが、信二は逃げ出したい気分だった。居心地が悪い。
その後もユニット曲がいくつか続いた。いい曲もあったが、滑り出しのせいで信二はどこか他人事だった。間にはさまれるトークも、彼女たちについて深く知らない信二にはわからないことが多かった。彼は地球の反対側のニュースを観ているようにさめていたのだった。
だから伊吹翼が出てきたときも、彼は冷静に演技を見ることができた。日常と共にあるはずのクラスメイトは、非日常の舞台の中にいた。
ウエストの細い衣装だとスタイルの良さが際立つ。短いスカートからのびる脚は繊細な曲線で、同時に健康的な肉づきだ。短めのネクタイは豊満な胸部の上でぴょこぴょこはね、観衆の視線を釘づけにする。遠くから見ても整った顔はメイクでシャキっとして見えるが、笑った顔のみずみずしさは寸分たがわず彼女だった。
3人ユニットで歌うのは、冬を先取りした恋の曲。恋に恋する乙女たちの喜びだった。
電子オルガンが飛びはね、フォーメーションは軽やかだ。信二は、伊吹によく似合っていると思った。ぼろきれのように使い古されたテーマなのに、等身大の歌詞がいさぎよくて華やかだ。
相手よりも自分のための恋愛。そんな自分勝手なところが苦手だったはずなのに、信二は彼女たちを魅力的だと思ってしまいそうになった。ありのままの伊吹翼の魅力を認めてしまえば、何も言い訳をすることができなくなる。それをどこかわかっているのか、信二は耐えきれなくなって目をそむけた。
春なんて来なくていい。ずっと冬のままでいい。彼が視線をよけた先には、真っ暗な床と椅子の背だけがあった。信二の気持ちとは関係なく、ステージの証明はピカピカ光っていた。
いつの間にか伴奏は終わっていて、ステージに翼の姿はなかった。MCの時間だ。アイドルが数人で話している。
だが、さっきの演目が焼き付いた信二の脳みそには、会話の内容は入っていかなかった
それからは個人曲が続いた。雰囲気をみるに、ライブも後半戦なのだろう。個性が前面に出た曲の数々だ。歌もダンスも仕上がっている。ユニット曲がおざなりというわけではないだろうが、アイドルの表情にも一層、力が入っていた。
1人、また1人と歌い終わるたび、信二はびくびくしていた。伊吹翼の番となったとき、何かが決定的に変わってしまうのではないか。そんな予感があったのだ。もう彼は、ここにやって来た経緯すら忘れていた。
背の低い三つ編みのアイドルが、外見に似合わぬセンチメンタルな曲を歌い終わったあと、そのイントロは流れた。
信二は、なぜだかそれが彼女の歌だということを直感した。
会場は季節を逆行し、炎天下の甲子園球場に変化した。肌を焼き輝く太陽は、ステージに現れた彼女自身だ。
真っ白なライトに照らされた伊吹の手にあるポンポンは、キラキラとまたたいているが、彼女の前ではかすんでしまう。チアガールのように踊る伊吹は会場中で、誰より輝いていて、誰より真剣だった。観客の視線はこの時間、彼女だけに注がれる。伊吹はそれに笑顔を返すと、あざといくらいに無垢なダンスを披露する。甘い歌声は鈴の音のようで、魅了の魔法が発動していた。
信二は知らず涙を流していた。自分勝手な青い恋と、刺すようなひたむきさ。それらが両立することを突き付けられていた。
伊吹翼という少女の真っ直ぐさ。信二はそれを言葉にできないほど感じていた。彼女の真剣さは、信二が今まで感じていた彼女のだらしなさと矛盾しない。伊吹翼は常に自分だけの空を精一杯羽ばたいているのだった。
信二が今まで理解できなかったものの片りんに触れると同時に感じたのは、しかし疎外感だった。クラスで毎日のように顔を合わせている少女が、どうしようもなく遠い。彼女は太陽のように明るくて、太陽のように離れていた。自分が気付いていなかっただけで、伊吹はずっと違う世界に住んでいたんだろう。信二はそう思った。そうしないと、ステージ上のアイドルをずっと見ていたいと感じる自分の気持ちと折り合いをつけられなかった。
伊吹翼は自分とは全く違う存在である。
それが信二の出した結論だった。これは改心であり祈りであり、そして逃避であった。
変な宗教にでもはまってしまった気分だ。
信二は舞台に咲く女神に、伊吹翼という名前を付けたのだった。
***
「ごめん、俺が間違ってたよ」
それが、講演が終わった直後に信二が慧介に告げた言葉だった。間違っていたことがたくさんあって、でもどこまでが間違いなのかわからなくなっていた。
そう言われた慧介は、涙のかわいた跡が残る顔をほころばせる。
「え? うん、そうだな。このみさんのdear…最高だったよな」
風に吹かれるこげ茶の葉が、ひらりとアスファルトに落ちた。
おわりに
感想があると大喜びしますので、書いてもいいよという方はここかカラスムギ(twitter:@karasumugi_imas)までお願いしますm(_ _)m
明日はクレスさんの記事になります、お楽しみに!
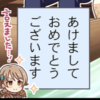






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません